― 自分とは何者か。問いながら、それでも進んでいく少女の物語 ―
はじめに|キキはなぜ旅立ったのか?
映画『魔女の宅急便』は、ジブリ作品の中でも、穏やかで優しい世界観が広がっているように見えます。
けれどその本質は、もっと深く、もっと切実な物語です。
キキの旅立ち
13歳になったキキは、魔女の伝統に従い、親元を離れて一人旅に出ます。
それはただの「修行」ではありません。
「自分とは何者か?」という問いを携えながら、彼女は人生で初めて、“ひとり”で社会の中に立とうとするのです。
根拠なき自信と揺らぎ
魔女としての自分にどこか自信がありました。
それは、子どもならではの、根拠のない、でもまっすぐな「私はできる」という感覚。
けれどその自信は、出会う人の数だけ揺らぎ、社会という複雑な海のなかで、簡単に波に飲まれていきます。
見知らぬ街で、魔女としての「自分」を試される
キキがたどり着いたのは、海の見える中規模の街。
親切なパン屋の奥さん・おソノさんに助けられ、空を飛ぶ能力を活かした「お届け屋さん」として暮らし始めます。
最初の順調さ
最初は順調でした。
荷物を運ぶたびに、人の役に立っている実感があったし、感謝されることが自信にもなっていた。
けれど、社会というのは、それだけではありません。
失敗と疑問の芽生え
時間を間違えたり、うまく届かなかったり、感謝されなかったり、失敗したり。
そうした経験が重なるにつれ、「私は本当に魔女としてやっていけるのか?」と、疑問が心に巣くっていきます。
「人の感情」に振り回されるということ
思えば、キキはそれまで“魔女”というアイデンティティのもとに育てられてきました。
「飛べる」という能力は、彼女にとって“特別であること”の証でもあった。
社会に出て知る現実
でも、社会に出て人と関わるうちに、彼女は気づいていきます。
特別であることが、時に人を遠ざけるということに。
期待されることが、時に自分を追い詰めるということに。
優しくされたと思えば、急に突き放される。
そんな「人の感情」という見えない波に、キキはどんどん翻弄されていきます。
飛べなくなることの意味
そしてついに、「飛ぶ」という魔女として最も大切な能力を失ってしまう。
これはただの「魔法の不調」ではありません。
“自分は何者か”という根っこが揺らいだとき、人は、自分の本来の力を失ってしまう。
それは、魔女でなくても、誰しもが一度は経験することかもしれません。
迷いのなかで出会う他者のまなざし
そんなキキを、ある画家の女性・ウルスラが山小屋に迎えてくれます。
彼女もまた、創作という“見えない力”を信じ、日々自分と向き合い続けている人。
ウルスラの言葉
彼女の言葉は、単なるアドバイスではなく、深い共感と励ましに満ちていました。
「描けなくなるときだってあるわよ。でも、それも全部、自分なんだよね。」
自分を受け入れる
飛べなくなった自分も、自分。
うまくできない自分も、自分。
逃げたくなったって、いいじゃない。
ウルスラのまなざしのなかで、キキは少しずつ、曇っていた心に風を通していきます。
「どうしたいか」で動いたとき、力は戻る
物語の終盤、トンボが気球事故で空中に取り残される場面。
あの瞬間、キキは迷いながらも、自分の心に従って走り出します。
「助けたい」――ただ、それだけ。
打算も、過去の失敗も、恐れも関係ない。
その思いが、もう一度、空を飛ばせる力を呼び覚ますのです。
飛ぶ意味の変化
最初に飛べたときと、再び飛べたとき。
同じ「飛ぶ」でも、そこにある意味はまったく違っていました。
- 前者は“根拠のない自信”
- 後者は“迷いと向き合ったあとに芽生えた確信”
人の感情を知り、社会の複雑さに傷つき、それでも「自分がどうしたいか」を見つけたからこそ、キキは本当の意味で“魔女”になったのだと思います。
終わりに|飛べなくなったときこそ、旅のはじまり
この映画は、飛ぶことの気持ちよさを描いた作品ではなく、「飛べなくなること」の意味を描いた物語だと思います。
失敗と迷いも旅の一部
飛べないときがある。
うまくいかないときがある。
人と比べて、自分が嫌になることもある。
でもそれは、自分を知るための旅の途中なのだと。
たとえ空を失っても、地に足をつけて歩くことをやめなければ、いつかまた風は吹いてくる。
希望をやさしく伝える物語
キキの物語は、そんな希望を、やさしく伝えてくれるのです。


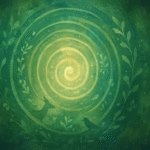





コメント