※この記事では、「色」や「空」といった『色即是空』の概念を扱っています。
※「色」と「空」、そして『色即是空』の意味をより深く知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。
言葉にしたくなる「感動」のあとで
映画でも、演劇でも、小説でも――
心に深く響いた作品を観たあと、誰かと感想を語り合いたくなることがあります。
「どうだった?」
「泣いたよね」
「わたし、あの場面が…」
それらは、ごく自然なやりとりです。けれど最近、ふと思ったのです。
本当に心を揺さぶられたときほど、言葉にしない方がよいのではないかと。
それは、言葉にすることで「何か大切なものがこぼれ落ちてしまう」ような、
そして、誰かに伝えた瞬間に自分の中にあった震えそのものが消えてしまうような、そんな感覚です。
空に響いた感動を、色に変換することの危うさ
私にとっての感動とは、「空」に咲いた花のようなものです。
そこには、言葉になる以前の感情や気配、気づきが静かに広がっている。
そんな「空」に響いた体験を、言葉という「色」に変換し、誰かに伝えようとした瞬間、
調和が崩れ、不調和な響きが生まれてしまうことがあるのです。
それはなぜか。
私という存在(色)が、感動という空に触れ、
その空を表現するために「言葉」という色を使う。
けれど、一緒に観ていた相手もまた、別の色を持ち、別の空を抱えている。
つまり、同じ体験を共有していても、内側で受け取ったものはまったく違う可能性がある。
それを言葉にしてしまうと、かえって「ズレ」が露呈し、
互いの空がぶつかり合うような違和感が生まれてしまう。
それは、とても繊細な「空虚」です。
感動はただ、そこに置く
だからこそ、私はこう思うようになりました。
一緒に観た人には、「感動したね」「面白かったね」だけで、じゅうぶん。
その一言の裏には、「同じ時間を、同じ場を過ごした」という共有がある。
そこに余計な言葉を重ねないことで、むしろ美しい調和が保たれるのです。
言葉にならない感動は、言葉にしないままでいい。
それは、自分だけの静かな余韻として、心の奥にしまっておく。
響かなかった、あるいは難解な作品は、むしろ語れる
面白いことに、逆のケースとして、
心に響かなかった作品や、難解な作品については、案外スムーズに語り合えることがあります。
たとえば――
「なんだか物足りなかったね」
「展開が読めてしまった」
「もう少し深く掘り下げてほしかった」
「難しくて意味はわからなかったけど、それが面白かった」
といった感想です。
なぜ、感動しなかったり、難解だった作品のほうが語りやすいのでしょうか。
おそらくそれは、「空」が震えなかったから、あるいは、震えていたとしても何によって震えたのかが掴めなかったからです。
つまり、そこには深い“空(くう)”が存在せず、言葉(色)で容易に埋めることができる状態にあった。
あるいは、“空”は確かに動いたのに、その揺れの正体が見えない状態にあった。
そして、そうした空虚さや難解さに対しては、言葉もまた空虚あるいは抽象的になり、
かえって調和が取りやすくなるのです。
感動のような“内なる揺らぎ”ではなく、分析や批評といった“外側の視点”から語ることができるため、
感情がぶつかり合うことも少なく、むしろ建設的な会話として成立しやすいのだと思います。
言葉にすべきかどうかの判断は、「調和」にある
このように考えると、「言葉にすべきか、しないべきか」は、
調和が保たれるかどうかを基準に見えてきます。
– その言葉は、自分の空を守るだろうか
– 相手の空とぶつからないだろうか
– 言葉が調和を崩してしまわないだろうか
ときに、言葉にしないという選択は、もっとも美しい表現になります。
それはまるで、
花が咲いているのをただ見つめるように、
音楽を聴いたあと、静かに深呼吸をするように、
感動を「言葉にせず味わう」ことなのです。
おわりに 〜言葉の力と限界を知るということ〜
言葉は素晴らしい道具であり、誰かと世界を分かち合う手段です。
けれど、すべてを言葉にしてしまうと、大切なものをこぼしてしまうこともある。
とくに感動という“空に咲いた花”のような体験は、
無理に色に変換せず、そのまま抱いておく勇気が必要なのかもしれません。
「伝えること」と「伝えないこと」のあいだにある静かな調和。
その感覚を持つことが、他者と、自分と、より深くつながる道なのだと、私は思います。

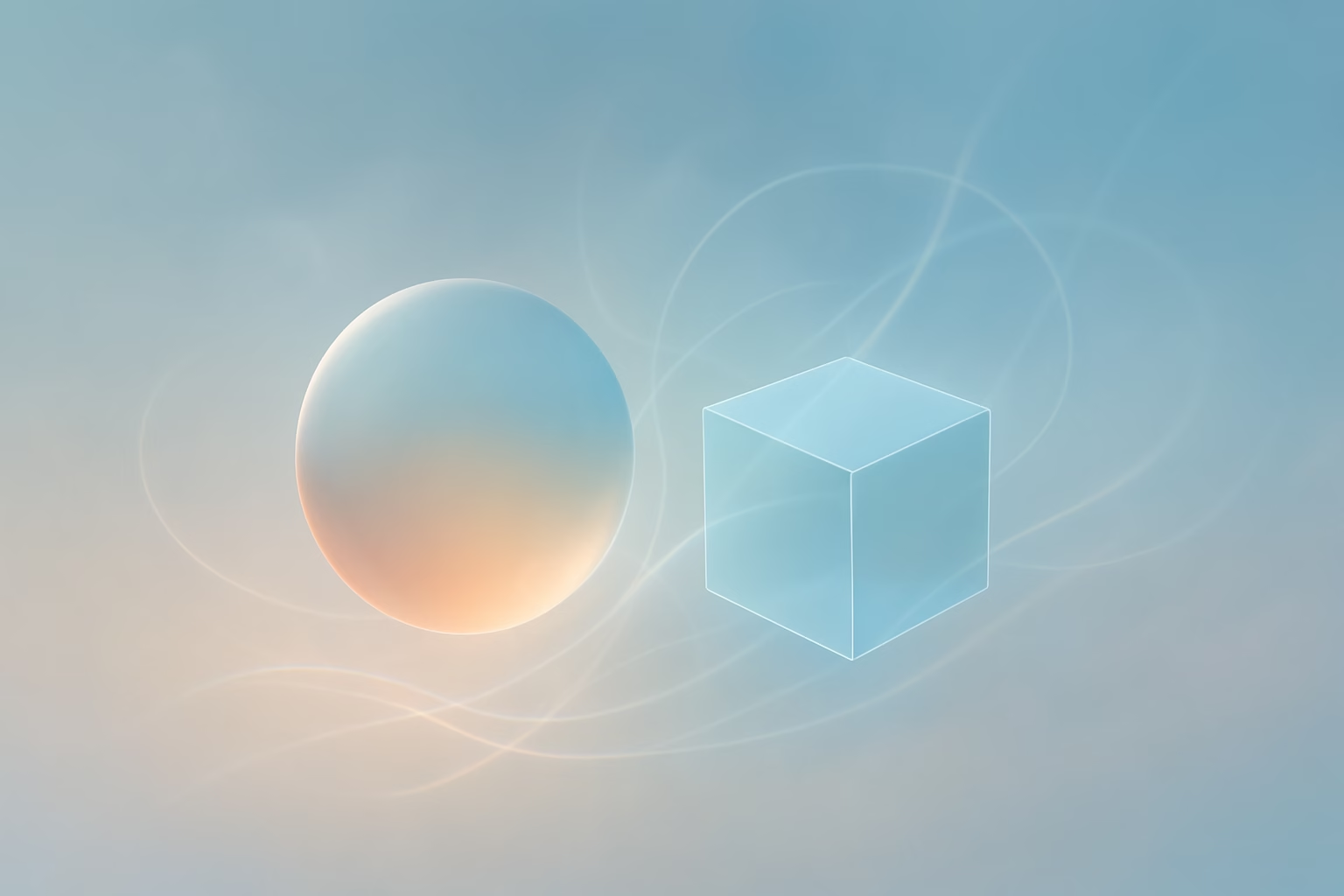






コメント