 致知感想
致知感想 【致知11月号・感想】特集「名を成すは毎に窮苦の日にあり」──名を成すは、母のように
『致知』11月号「名を成すは毎に窮苦の日にあり」を読んで思い出した母の姿。名を求めず、与え続ける母の生き方から、“名を成す”本当の意味を見つめ直すエッセイ。
 致知感想
致知感想  書籍と向き合う
書籍と向き合う  書籍と向き合う
書籍と向き合う  映画と向き合う
映画と向き合う  映画と向き合う
映画と向き合う  書籍と向き合う
書籍と向き合う 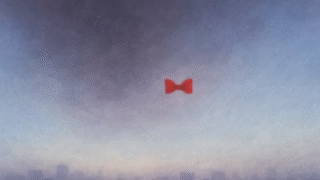 映画と向き合う
映画と向き合う  書籍と向き合う
書籍と向き合う  書籍と向き合う
書籍と向き合う  夏目漱石『こころ』
夏目漱石『こころ』