朝礼で気づいた、帰りがけの挨拶の意味
日常に潜む挨拶の力
ある日の会社の朝礼。恒例となっている「1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書」の朗読を聞いた。題は「帰りがけの挨拶をみておくように」。
普段は何気なく交わしているお見送りの挨拶にも、深い意味があることに気づかされました。

挨拶が残す余韻
挨拶ひとつで、相手の心にどんな余韻を残すのか。
ほんのわずかな距離や所作の差が、見えない心の糸を張り、次の出会いを静かに導くのだと感じました。
風に運ばれる心の距離
出迎え三歩、見送り七歩
古来、日本には「出迎え三歩、見送り七歩」という所作があります。
客を迎えるときは三歩だけ進み、見送るときは七歩を歩む。それだけのことなのに、そこには目に見えない心の交流、静かなリズムが刻まれています。
心の距離の意味
三歩は、相手に寄り添う距離。
七歩は、少し先まで見送り、余韻を残す距離。
このわずかな差が、心の貸しと返しのリズムを生み、途切れない関係を育むのです。
見えない糸が結ぶ次の出会い
人の心に風が吹き、見送るたびに見えない糸が張られる。
そして次に会うとき、その糸は静かに引き合うように人々を導きます。

数字が奏でる調和の旋律
三の意味
三は安定を象徴します。三本の柱が屋根を支えるように、三歩は迎える心の安定を示します。
七の意味
七は循環と余韻を象徴します。七曜、七福神、七五三……生活のリズムや人生の節目を形作る数字です。
三と七が作る心の調和
出迎えの三歩は関係の基盤を支え、見送りの七歩は次の出会いへの余白を残す。
三と七が奏でる旋律は、見えない調和をつくり、心の奥に穏やかなリズムを刻むのです。
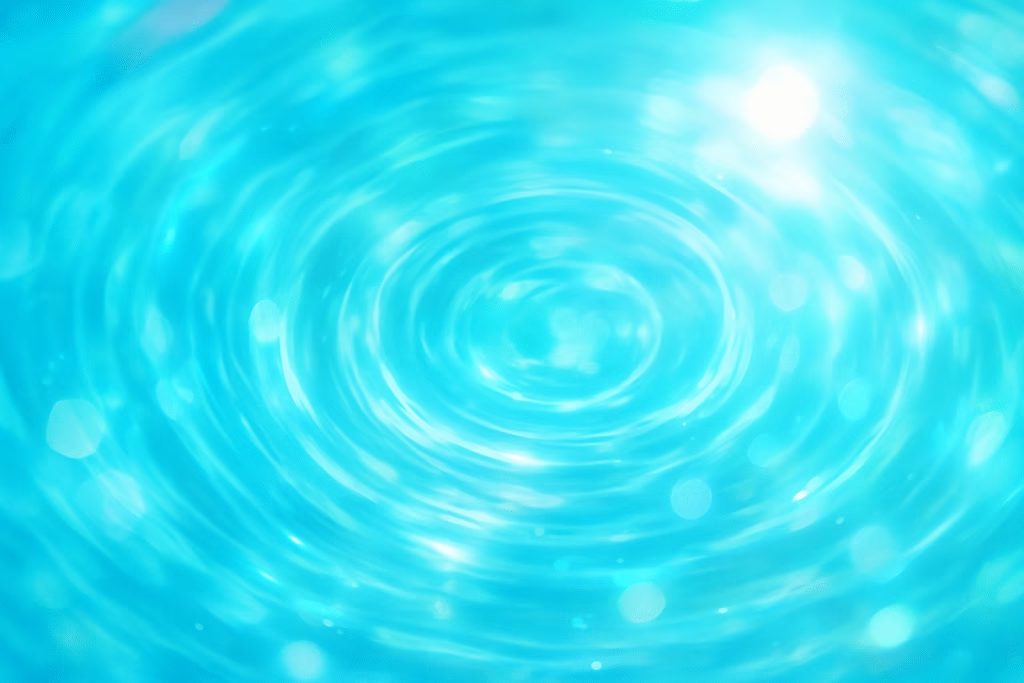
見えない「貸し」と「返し」の糸
返すべき糸の存在
見送られた人は、知らず知らず「少しの貸し」を受け取ります。それは形には残らないけれど、次に会うための理由となる糸です。
出迎えの三歩の控えめな意味
返すべき糸があるから、人はまた顔を見せ、言葉を交わす。
出迎えの三歩は、その糸が返ってくることを知っているから、控えめに待つ。
人間関係の川のような循環
こうして貸しと返しの糸は、ゆるやかに循環します。
人と人の関係は、川の水のように途切れず流れ、柔らかくも確かなつながりをつくるのです。

縁起を意識する日本の所作
行為がつながる縁起の思想
この所作は、仏教的な縁起の思想にも通じます。
私たちの関係は、互いの行為がつながり、影響し合うことで成り立っています。
心の呼吸としての挨拶
出迎えと見送りは、縁を意識化するひとつの儀式であり、心の呼吸でもあるのです。
風に揺れる葉のように、互いの心を少しずつ運び、次の出会いを予感させます。
調和の種としての余韻
心に余韻を残すことが、調和の種となり、縁を途切れさせません。
余白の美学
忙しい日常で失われがちな余白
現代の忙しい日々、人はつい効率や時間に追われ、関係を消費してしまいがちです。
数字以上の感覚としての所作
三歩と七歩の所作は、数字以上の感覚、余白の美学を教えてくれます。
急がず、先を求めず、静かに相手を見つめ、見送る心に余韻を残す。
余白が育む次の出会い
余白とは、沈黙の中の呼吸のようなもの。
言葉にならない思い、形にならない感情、それが次の出会いを育てます。
人間関係は見えない糸の流れ、心の余白で支えられているのです。

風景の中に息づく所作
季節の移ろいと心の変化
春の花、夏の陽、秋の風、冬の雪──季節が移ろうように、人の心も絶えず変わります。
小さな行為の大きな意味
出迎え三歩、見送り七歩の所作は、そんな変化の中でも途切れない縁を紡ぐための、静かな呼吸です。
目に見える行為は小さくても、その背後には深い意味がある。
人と人を結ぶ柔らかな力
それは、風が草木に触れ、光が水面に揺れるように、柔らかくも確かに、人と人を結び続けます。

まとめ
帰りがけのほんの一瞬の挨拶にも、心を運ぶ力があります。
「出迎え三歩、見送り七歩」は、単なる礼儀や作法ではなく、
安定と循環、貸しと返し、余白と縁――すべてを内包する、途切れない人間関係の智慧です。
今日の朝礼での気づきは、こう教えてくれました。
小さな一歩の余白が、心の距離を運び、縁を紡ぐ。
見えないけれど、確かに流れる心の糸が、次の出会いへとつながるのだと。








コメント