※この記事では、「色」や「空」といった『色即是空』の概念を扱っています。
※「色」と「空」、そして『色即是空』の意味をより深く知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。
『奇跡の社会科学』との出会い
こんにちは。たきです。
今日は一冊の本を通して、自分自身の内側を深く見つめ直した時間について綴ります。
その本の名前は中野剛志著『奇跡の社会科学』。
読んでいる最中、何度もページを閉じては、静かに天井を見つめるような時間がありました。
心がざわつくというより、「いまの自分の立ち位置」を問われ続けているような感覚でした。
この文章は、その読後の“沈黙”の中から、ゆっくり掘り起こした言葉たちです。
自由は本当に、望んでいたものだったのか?
私たちは、自由を求めます。
誰にも縛られずに、自分で選び、自分で決める人生。
その響きには、美しさと正しさがあります。

自由の響きとその現実
でも、本当にそれは“幸せ”だったのでしょうか?
- 「自由に働けるようになった」
- 「どこにいても仕事ができるようになった」
- 「選択肢が増えた」
こうした変化の中で、私たちの生活は豊かになったはずでした。
でも、心のどこかにぽっかりと空いたような“孤”が残っていることに、気づいている人も多いのではないでしょうか?
自由の逆説
選択肢が増えれば増えるほど、なぜか不安になる。
どこにも縛られていないのに、なぜか何かに追われている気がする。
それは、「自由になったはずなのに、自由でなくなっている」という現象そのものです。
孤にされた自由──その隙間に入り込むもの
自由を求めるという行為は、ときに「関係性を断つ」ことでもあります。
誰かに依存せず、自分の足で立つということは、裏を返せば「支えられない」ということにもなる。

美徳と冷たさ
それは美徳のように語られるけれど、現実にはとても冷たいものです。
グローバリズムの影
そして、その“孤”にされた心の隙間を、そっと、しかし確実に狙ってくるものがある。
それが、グローバリズムです。
- グローバリズムは、「世界はひとつになれる」と言います。
- 「自由で、開かれた社会こそが、進歩だ」と語ります。
でも、その正体は、すべての価値を“交換可能なもの”に変える装置です。
家族の時間より、労働時間。
伝統より、効率。
愛より、論理。
私たちは、自分の大切なものを少しずつ、差し出すようにして手放してきたのかもしれません。
自由であることと引き換えに。

「色」に執着すれば、「空」になる
ここで私は、ふと仏教の言葉を思い出しました。
色即是空、空即是色
これは、「目に見えるすべてのもの(色)は、実体がなく空である」という意味。
そしてその逆もまた真なり──「空から、形(色)は生まれる」。
自由の形への執着
自由を「形」にしようとするから、私たちは苦しくなるのです。
- 理想の働き方
- 理想の生き方
- 理想の自分像
そういった“色”に執着することで、かえって自分を見失っていく。
「こうあらねばならない」と思えば思うほど、「本来の自分」が遠のいていく。
それは、自由の仮面をかぶった強迫に他なりません。

つながりを求めすぎることもまた、煩悩になる
自由だけじゃありません。
つながりもまた、現代社会においては一種の“商品”になっています。
数値化されたつながりの罠
- 「いいね」をもらう数
- 「フォロワー」の数
- 「共感」してくれる人の多さ
そうした“数値化されたつながり”を求めるあまり、私たちはいつの間にか「人との関係」すら、“自己演出の場”にしてしまったのかもしれない。
そして、繋がるために無理をして、笑って、迎合して、気づけばそこには「自分」がいない。
これは、自由を求めたときと同じ構造です。
「つながり」もまた、執着すれば煩悩になり、やがて空になる。
私たちに必要なのは、「問い」続けること
では、私たちはどう生きればいいのでしょうか?
自由も、つながりも、簡単に“空”になるのなら、何を信じればいいのか。
小さく確かな答え
そのとき浮かんだ答えは、とても小さく、けれど確かなものでした。
それは、
「問い続けること」
です。
- 自由とは何か?
- つながりとは何か?
- 関係性とは何か?
- 自分とは、誰か?
それらに「答え」を出すことではなく、「問い続ける姿勢」にこそ、人間らしさが宿る気がします。
完璧な自由も、完全なつながりも、きっと存在しません。
でも、その不完全さの中に身を置きながら、「関係性を編み続ける」こと。
それこそが、社会の“奇跡”なのだと思います。
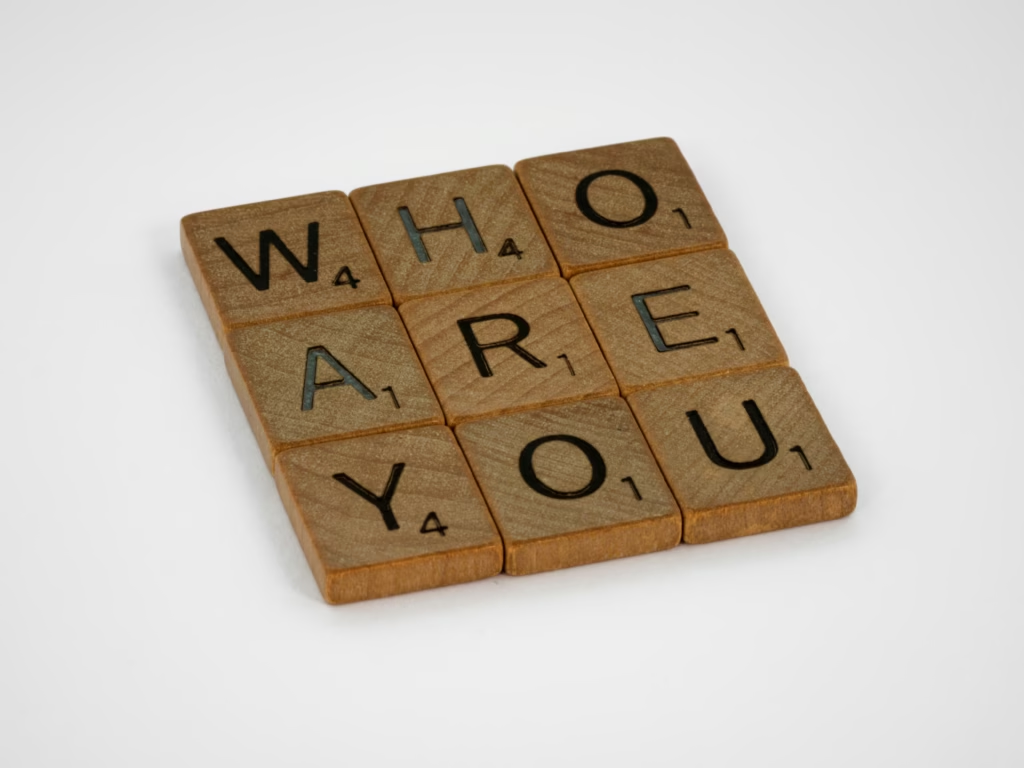
空に、まれに咲く──問い続けるという花
すべてが“空”になってしまうような世界のなかで、
それでも関係性を手放さず、問い続ける姿は、美しい。
それはまるで、
どこまでも広がる空の中に、まれに咲く、一輪の花のよう。
花のように問い続ける
その花は、すぐに散るかもしれない。
誰にも気づかれないかもしれない。
でも、それでも咲こうとする。
そんな花のように、問い続け、編み続け、関係し続けること。
それこそが、私たちに残された、本当の自由なのかもしれません。









コメント