「伝えること」への執念
日本という国は、なにかを「表現すること」に関して、恐ろしいほどの貪欲さを見せてきました。
その貪欲さは、時に柔らかく、時に執念深く、時にしなやかに。
そしてそのどれもが、「伝えたい」「表したい」という人間の根源的な欲求に突き動かされているように思います。
この国は、「伝えるためなら、なんでも使ってやる」とでも言うように、あらゆる文化や形式、文字や感性を取り込んできました。
それはただの吸収ではなく、自らのフィルターを通した“編集”によって、新たな表現の形を次々と生み出してきたのです。
四つの文字が共存する言語
たとえば、言葉ひとつとってもそうです。
日本語は、世界でも稀に見る「多様な文字が共存する言語」です。
- 漢字(意味を担う)
- ひらがな(感情や音のやわらかさを表す)
- カタカナ(外来性や強調を示す)
- アルファベット(ブランド、略語、科学語など)
これらを場面や文脈によって使い分けることで、より繊細で、より深みのある表現を可能にしているのです。
文字体系の違うものを、混ぜながら、壊さず、それぞれの「役割」を活かして使う。
それはまさに、「多様性の尊重」でありながら、「表現のための戦略的編集」とも言える姿勢です。
表現のための混血主義
日本文化は、外来の文化をそのまま取り入れることはほとんどしません。
取り入れるときには、必ず「自分たちの文脈」に落とし込んで再構築する。
たとえば──
- 仏教はインドから中国を経て渡ってきたが、日本では神道と融合し「神仏習合」という独自の形を作った。
- 建築も中国や朝鮮から技術を取り入れながら、最終的には木造と自然との調和を重視する和様建築に変化。
- アニメやマンガでは、西洋的ファンタジー世界に日本的価値観や感情の機微が融合され、世界から「JAPAN」として注目されている。
つまり日本は、混血を恐れず、混血の中にこそオリジナリティを見出す文化を育ててきたのです。
統一ではなく、編集するという思想
ここで注目したいのは、日本は決して「統一」しようとしないという点です。
国や文化を強くするために「一つにまとめる」のではなく、バラバラなものをバラバラのまま使いこなすという道を選ぶ。
それは、ある意味で非常に高度なことです。
違いをなくすのではなく、違いを「活かす」こと。
摩擦を恐れず、むしろその摩擦を表現のエネルギーに変えること。
日本文化の底流には、そんな「多様性と編集」の思想が静かに息づいています。
表現することは、生きること
なぜ、そこまでして表現にこだわるのか。
それはたぶん、日本人にとって「表現すること」は、「生きること」と密接につながっているからです。
曖昧なもの、移ろうもの、確定できないもの──
それらを、どうにかして伝えたい。どうにかして、言葉にしたい。形にしたい。
- 一枚の襖絵に季節の巡りを閉じ込める。
- 一つの料理に、土地と歴史の物語を込める。
- 一つの文章に、見えない感情の輪郭を描く。
そうやって、私たちは「生きていること」を、静かに、でも貪欲に、表現してきたのではないでしょうか。
終わりに:多様性とは、使いこなすこと
多様性を認めるというのは、ただ共存させることではありません。
それぞれを、場に応じて使いこなすことです。
日本文化が示してきたのは、まさにその「使いこなす」知恵と感性。
そしてそれは今も、私たちの言葉遣いや日常の中に、脈々と息づいているように思うのです。

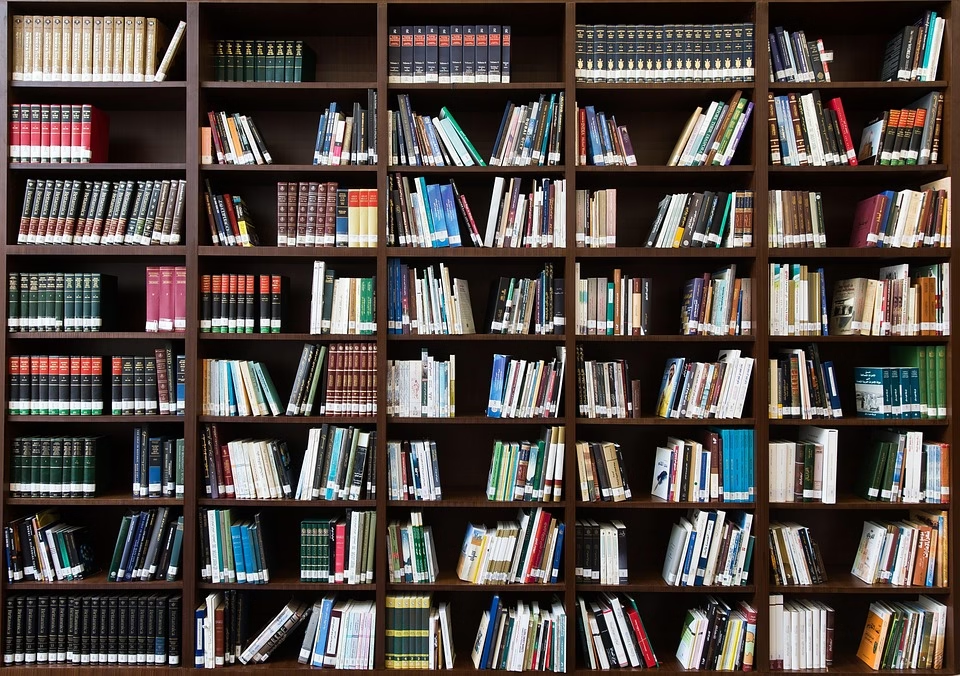






コメント